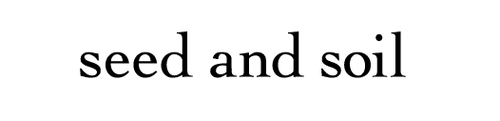プロであること。
勝ち続けること。
求められる自分でい続けること。
それらを一度手放しながらも、何度も“ 満たされる形 ”を選び直してきたサーファーがいる。ryobay。
彼女の人生は、常に海とともにあった。
東京で生まれ、サーファーの父の背中を見て育ち、週末は千葉で過ごすのが当たり前だった幼少期。当時の彼女が夢中になっていたのは、サーフィンよりも、砂遊びや自然の中での“遊び”そのものだった。
『サーフィンとの出会い』
 Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
小学6年生になると、いつもの砂遊びは少しずつ形を変えていく。
ボディーボードを手にし、海に浮かぶ時間が増えていった。
ある日、太東ビーチでのこと。
波は驚くほど小さく、ボディーボードすらままならない穏やかな日だった。
そんな様子を、周りで見ていた大人たちが声をかける。
「このスポンジボードで、サーフィンやってみれば?」という、何気ないひと言。
けれど、その瞬間が、彼女の時間をゆっくりと動かし始めた。
初めて立った、波の上。体の下をすべっていく水の感覚。
前に進んでいく、不思議な浮遊感。
言葉にできないほどの気持ちよさを、
彼女はその時、確かに感じていたという。
この日をきっかけに、ryobayはロングボードに惹き込まれていった。
 Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
ちょうどその頃、父はサーフショップを始めた。
気づけば、サーフィンに打ち込むための環境は、自然と整っていて、海とともに過ごす日々は、いつしか彼女のライフスタイルの中心になっていた。
数年が経ち、高校を卒業。
毎年家族で訪れていたハワイで、
三ヶ月間、じっくりと滞在する時間を過ごした。

そして19歳のとき。東京から千葉へ、本格的な移住が決まった。
昔から通い、顔なじみの人も多いこの場所で、
アルバイトをしながら、ただひたすらサーフィンをする日々。
波に合わせて起き、海に入って、バイトへ駆け込み、また次の日を迎える。アルバイトとサーフィンを繰り返す生活だったという。
そんな生活の中で、彼女の胸に、ひとつの小さな感情が芽生え始めていた。
「試合に、出てみたい。」
『プロへの道』
 pc Honey magazine (雑誌 HONEY の撮影で訪れたタイ・プーケットでの1枚)
pc Honey magazine (雑誌 HONEY の撮影で訪れたタイ・プーケットでの1枚)
彼女はすぐに行動し、小さな試合から実践してみることに。
いつもの海とは違う緊張感。
限られた時間。
見られるという感覚。
そのすべてが、彼女にとっては新鮮で、少しだけ心をざわつかせるものだった。
「当時は純粋にサーフィンがうまくなりたかったんだよね。試合に出てから、まだ若かったし、勝ちたいとか、悔しいとか、そういう感情ばっかりだったね笑」
彼女の中で芽生える新しい感情が、少しずつ積み重なっていく。
選手としての感覚が育っていく中で、ryobayはひたすら練習に向き合っていたという。
 「当時は、女子のロングボードにプロ制度がなかったんだよね。大会といえばアマチュアのみで、試合で勝つのはいつも同じ先輩たちだったの。」
「当時は、女子のロングボードにプロ制度がなかったんだよね。大会といえばアマチュアのみで、試合で勝つのはいつも同じ先輩たちだったの。」
そんな中、ふと耳にした会話があった。
「私たちが大会に出続けていたら、下の世代の子たちが育たないよね。」
「ショートボードみたいに、プロツアーがあってもいいのにね。」
そんな会話が彼女の耳に静かに残った。
数年が経っても、状況は全く変わっていなかった。
ryobay自身もいつしか、どの大会でも名前を呼ばれる存在になっていた。
「NSA第41回全日本サーフィン選手権大会」、「NOOSA Festival of Surfing」。
「ASP(現WSL) RealBvoice ProLongboardTAITO」など数多くの大会で タイトルを勝ち取り、実力を伸ばしていた。
かつて求めていたはずの景色だったが、同時に、小さな違和感のようなものが胸の奥に残り始めていたという。
「自分が試合で勝てるようになって、先輩たちが言っていたこと、その通りだなって、ふと思い出したんだよね。自分が出続けていたら、下は育たない。それに、私たちより若い子たちに続いていかないと、ロングボードの女子っていう、この狭い世界は広がっていかないなって思ったの。」
それは、静かに彼女の中で立ち上がってきた、ひとつの実感だった。
 Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
その頃のryobayは、メディアに取り上げられ、さまざまなスポンサーと契約し、
世界各地でサーフィンをする日々を送っていた。
そんな日々を過ごしていた、23歳の頃。そんなタイミングで、彼女はひとつの決断をする。
長年、先輩たちが実現できずにいた「ロングボードのプロツアー実施」について、
自ら連盟に申し出たのだ。
そしてそれも、女子ロングボーダーとして活躍していた彼女の案は、すぐに通った。
「当たり前だけど、ryobayももちろんプロの試合に出るんだよね?」と連盟に導かれ、プロ公認試合を経て、ロングボード女子プロツアー1期生として、ツアーを回ることになった。
「当時は、そんなにプロツアーに出たいと思ってたわけじゃなかったんだよね。
次世代のために、あった方がいいとは思って申し出たけど、まさか自分がツアーを回ることになるなんて、思ってもいなかった笑 でも、言ってしまったからには、それは出なきゃだよね笑」
そう話しながら、彼女はどこか照れくさそうに笑った。

『本当にしたいサーフィンとは』
プロとして、約三年間、ツアーを回ったryobay。
全国各地、全世界を移動し、試合のために海へ向かう日々。
朝早くから会場に入り、ヒートの時間を待ち、限られた波に集中する。
勝つこともあれば、思うようにいかない日もあった。
それでも、プロとして求められる役割を、彼女はひとつひとつ、丁寧にこなしていた。
周囲から見れば、順調なプロキャリアに映っていたかもしれない。
けれど、そんな日常を重ねるうちに、心の奥に、言葉にしづらい感覚が残るようになっていった。海に向かう足取りが、以前とは少し違って感じられる瞬間が、増えていったという。
「ある時から、競技っていうものに、だんだん疑問が湧いてきちゃって。
やっぱり私の性格上、サーフィンで競うことは好きじゃないんだなって、その時改めて気づいたんだよね。」
「限られた時間で波に乗ること。必ずしも良くない波のためにお金を払って試合に出て、
さらにジャッジされて勝敗が決まること。勝つために練習はするんだけど、そんなサーフィンが、だんだん楽しくなくなってきちゃったんだ。」
彼女の心の奥に、「私がしたいサーフィンは何だろう」と疑問が芽生え始めた。
 Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
その違和感は徐々に確実なものへと変わっていき、
ryobayは、試合に出ることをきっぱりと辞めた。
『満たされるということ』

それでも、サーフィンとの関わりが途切れることはなかった。
これまで関わってきたメディアやサーフィン業界の人たちとの仕事は続き、彼女の周りには、変わらず海を軸にした時間が流れていた。
試合という枠から離れたことで、ryobayは、自分が本当に求めていた
「プロサーファーの在り方」に少しずつ近づいていったという。

pc Deus (BALI島・チャングーにて招待試合での1コマ。自身のキャリアの中でもトップに入る好きな写真。shot by DEUS)
「試合に出ることを辞めてから、疲れていた心がなんだか軽くなったんだよね。試合じゃないプロサーフィン業が形になって初めて、この時のわたしが一番 “プロサーファー” をしてるなって思えたの。」
その言葉は、達成感というよりも、深く息をついたあとのような、静かな実感に近かった。
「思い返せばあの時、自分がちゃんと満たされていたんだと思う。」と振り返るように話した。
「サーフィンを通して、いろんな国を旅して、時には船の上で生活することもあったし、
良い波に出会っては、毎日のように興奮してた。応援してくれているファンの人たちもいて。
試合で勝つことだけじゃなくて、サーフィンっていう、自分の表現で誰かを喜ばせることができている感覚があったんだよね」
「それに、私のサーフィンを見てくれることで、見ている人のサーフィン感が少しでも広がっていく。そのお手伝いができていることが、すごく幸せだったかな。」
勝敗でも順位でもなく、誰かと比べる必要もない。
ただ、自分が好きな波に向かい、自分の感覚で板を走らせる。そしてそのサーフィンが、映像や写真、言葉を通して、誰かのもとへ届いていく。
そうした一つひとつの時間が、彼女の心の奥の部分をちゃんと満たし、さらに周りも満たしていけることを肌で感じることができたという。
『プロサーファーから母へ』
 Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
Wool calm sweater (taupe) & Boheme lounge pants (ethnic)
今も、地元の人に限らず、多くの人に親しまれているサーフショップ「YR」。
ここには、サーフィンを軸にした出会いや、ゆるやかな時間が流れている。
当時まだ26歳の頃、最初は一人で店頭に立ち、ショップ業務からスクールまでをこなしていたという。
その後、彼女の旦那さん、ユウタと結婚したことをきっかけに、2015年、二人で「YR」を立ち上げ、お店を営むようになった。
実は彼も、長年シーンを支えてきたプロサーファーの1人。
そんな二人が手がけるこの場所には、どこか安心感のようなものが漂っている。
お店を営みながら、それぞれプロとしての活動も続けていた。
次第に、プロ業とお店のことを考えながらの生活は、少しずつ彼女の呼吸を浅くしていく。プロとして活動する中で、「プロサーファーとしての姿」を求められる場面が、変わらず多くあった。
どんな波でも、美しくサーフィンすること。
期待を裏切らないこと。
そんなプレッシャーはいつまでもryobayを付き纏っていた。そこで彼女は一度立ち止まるように、大好きなハワイへ、二週間のリフレッシュの旅に出た。

「もうその頃は、ユウタと一緒にいて10年が経っていたし、いろんな景色を一緒に見てきて、いろんな波にも一緒に乗って、いろんな出会いがあった。ある程度、二人でできることはやってきたのかなって思ってたところだったんだ。」
ワイキキビーチで、ただ海を眺めながら、ぼんやりと時間を過ごしていた時、視線の先に、ひと組の家族が目に入った。
「自分たちより少し年上の夫婦と、2歳くらいの小さな子供が遊んでたの。砂浜で遊ぶ、ただそれだけの、なんでもない光景なのに、なんかすっごくよくて。」
ふとインスピレーションが舞い降りる。
「次は、もしかしたら、ユウタと私たちの子どもと三人で、また新しい景色を見ていくっていうのが、私にとって次の幸せなのかもなって、感じたんだ。」
自分を癒すために訪れたハワイは、気づけば、確信を抱えて帰る旅になっていた。
帰ってから彼に話したら、その気持ちを受け入れてくれたという。
そこから第一子を授かり、 三人での生活が始まった。

 (カピオラニパークでの挙式は私の願い)
(カピオラニパークでの挙式は私の願い)
「サーフィンができなくても、全然よかった笑」そう言って、彼女は少し間を置いた。
「違う世界に行っていいんだって、思えたんだよね。今までと違う自分に、変わっていけることが、すごく嬉しかったの。」
縛られていた “見られ方” からも離れられらたと話すryobay。
「きっと、自分は疲れてたんだろうね。今思うと、プロとしてやり切ったんだと思う。笑」
そう言って、彼女は静かに笑った。
その言葉には、自分の役割を全うした人だけが持つ、穏やかさがあった。
「子どもができてからは、不思議なことに、サーフィンで満たされていた部分が、全部子どもで満たされるようになったんだよね。」
それは、何かを失ったという感覚ではなく、自然と置き換わっていった、そんな実感だったという。
「子どもと一緒に海へ散歩に行くだけで、なんだか、自分がサーフィンしているみたいな感覚になれるの。」
 (心が喜び本当に贅沢でまた一つ夢が叶ったような時間、また家族で訪れたい場所KAUAI)
(心が喜び本当に贅沢でまた一つ夢が叶ったような時間、また家族で訪れたい場所KAUAI)
波の音を聞き、潮の匂いを感じる。
サーファーたちが波に乗る姿を横に、砂浜を歩く。
「出産もそう。本当に素晴らしすぎて!」彼女は目をキラキラ輝かせ、話を続けた。
「どんなに良い波に乗った時よりも、どんなに良いライディングをした時の充実感よりも、出産は、私が今まで味わってきた経験の中で、ダントツに、満たされた瞬間だったの。それにびっくりした。」
「生まれた瞬間、虹の橋がかかったような感覚。」
「そんな経験をしたからか、サーフィンをしていない時間も、ちゃんと満たされるようになっていったんだよね。」
それから、サーフィンへの執着は、気づかないうちに、そっと遠くへいっていたという。
「これからも、家族みんなが健康で、太陽を浴びながら、美味しいものを食べて、健やかに暮らしたいな。あとは、YRの形態も、これから少しずつ変えていけたらと思ってる。」
そう話す彼女の表情は、どこか穏やかで、肩の力が抜けていた。

最後に。
「自分が満たされていること」
それが、何よりも大切なのだと、ryobayの在り方は物語っている。
満たされる形は、ひとつじゃない。
人生のフェーズが変わっても、海との関係が形を変えても、彼女はいつも、自分にとっての“心地よさ”を手放さない。
それはきっと、誰にとってもヒントになる在り方だ。
“自分の心が満たされる選択を”
 Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
Wool calm sweater (oat) & Boheme lounge pants (oat)
Ryobay(瀬筒良子)
YR 顧問 / ロングボーダー
東京で生まれ育ち、18歳で千葉県いすみ市へ移住。
日本におけるプロロングボーダー第一期生として、コンテストをはじめ、サーフトリップでの撮影や執筆、イベントのプロデュースなど多岐にわたり活躍する。
コンペティションの第一線を退いた後は、
勝敗にとらわれないサーフスタイルや、
海と共にあるライフスタイルの発信へと軸足を移す。
「サーフィンを通して人生を豊かにすること」をテーマに、
サーフレッスンやイベント企画など活動の幅を広げ、自然体で美しいサーフスタイルと人柄で多くの支持を集めている。
現在は二児の母。
千葉県いすみ市・太東で営むサーフショップ「YR」を拠点に、
自身の経験を生かした Feeling Ocean Class を主宰。
海と波と戯れることの楽しさ、豊かさを感じてもらえるクラスとして高い人気を誇っている。
Article and photos by Hinako Kanda